kurupanです。
私は2級電気めっき技能士(技能検定 電気めっき 2級)の資格を持っています。
あまり知られていませんが、技能士は日本のものづくりを支えてきた、現場で働く際の技能の証明になる資格です。
本記事では技能士資格(技能検定)について解説していきます。
〇技能検定とは?
中央職業能力開発協会(JAVADA)のサイトには、以下の記述があります。
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
引用:JAVADA ウェブサイト http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html
ものづくりを行う上で、自身が持っている技能を証明するための検定が技能検定です。
〇メリットは?
職種・作業に関する一定レベル以上の技能を習得している証になります。
企業にとっては、自社のモノづくり力のレベルを証明する証になるため、HPなどに技能士の存在を記載し、アピールしています。そのため、多くの企業が社員に対して技能検定の受験を奨励しており、手当を支給している企業もあります。
また、一部の資格の受験資格となっていたり職業訓練指導員試験の実技試験を免除できたり(1級以上)します。
〇分類は?
全職種で111種類あり、機械加工からパン加工、造園まで幅広い分野の職種が設定されています。
一部の職種は複数の作業が設定されており、どの作業で合格してもその職種の技能士を名乗ることができます。
例えば、「機械加工職種」には「ボール盤作業」や「フライス盤作業」などの作業があります。
さらに、作業には等級が定められているものがあります。(作業によって等級の分けられ方は異なります。)等級には特級・1級・2級・3級・単一等級(等級なし)があり、特級が最も上級の資格になります。例えば、「ボール盤作業」の場合、特級・1級・2級があります。
該当する職種・等級の技能検定に合格することで、「〇級◇◇技能士」を名乗ることができます。例えば、私は「電気めっき作業」の「2級」に合格しましたので、「2級めっき技能士」を名乗ることができます。技能士は名称独占資格なので、技能検定の合格者以外は技能士を名乗ることはできません。
また、合格者には技能士章というバッヂが配布され、作業着等に着用することが許されます。
〇受験資格は?
受験するには(3級を除いて)関連する作業の実務経験が必要です。受験する等級によって、受験資格が異なります。
特級 1級合格後5年以上 1級 7年以上 2級 2年以上 3級 ※ 単一等級 3年以上 ※3級の受検資格として必要な実務経験期間については、従前6ヵ月以上とされておりましたが、平成25年4月から緩和され、6ヵ月に満たない場合も受検可能となりました。
引用:JAVADA ウェブサイト http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken.html
ただし、学歴や所有資格などにより、必要な実務経験の期間は短縮されます。例えば、2級の受験には2年間の実務経験が必要ですが、高校卒業以上の学歴を持ち、かつ受験科目に関連する学科・学部・研究科等の出身であれば、必要な実務経験は0年になります。また、下位の等級を持っていても短縮されます。
結構細かい決まりがあるので、JAVADAのウェブサイトで確認してください。
〇試験内容は?
技能検定の試験は、実技試験と学科試験に分かれているのが大きな特徴です。
実技試験は実際に該当作業を行い、その技能を試験員が判定します。
事前に該当作業に関する課題が公表され、決められた試験会場(工場や研修施設など)でその課題に取り組みます。
例えば、私が受験した電気めっき作業では、指定された物品に決められた膜厚のめっきを施したり、めっき液の組成を分析する課題が出題されました。すぐ近くで試験員が見張っているので結構緊張します・・・。
事前準備なしだと、なかなか難しい課題が多いです。事前に試験会場で練習会が設定されている場合がありますので、できる限り参加するようにしましょう。それだけで、合格率は大きく変わってきます。
学科試験はいわゆるペーパーテストです。該当作業に関する基礎知識を問う問題が出題されます。こちらはしっかりと勉強すれば、比較的合格しやすいです。
技能士のペーパーテストの勉強におすすめの問題集はこちら
〇合格基準は?
実技試験は60点以上、筆記試験は65点以上で合格となります。
実技試験は複数の課題を出題されますが、そのすべての課題を完璧にこなす必要はありません。1つの課題を失敗したとしても、あきらめずに最後までやり切りましょう。
〇試験日は?
8~9月にかけて行われる前期日程と1~2月にかけて行われる後期日程があります。実技試験と筆記試験は別の日に実施されます。
注意していただきたいのは、前期か後期のどちらかでしか受験できない職種があることです。自分の受験したい職種(作業)の試験日を確認しておきましょう。
〇申し込み方法は?
都道府県単位で申し込みを受け付けています。
受験を希望する都道府県の職業能力開発協会のHPから申請書を入手してください。
必要な書類とともに郵送するか、受付会場に持参することで申し込みすることができます。必要書類は以下の通りです。(注:必ず各都道府県の技能検定の実施案内を確認してください!)
- 受験申請書
- 受験手数料(郵送の場合は振り込み)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)(郵送の場合はコピー)
- 関係書類(実務経験の短縮を申請する場合は卒業・学位証明書など)
- 郵送内訳表(郵送の場合のみ必要)
なお、受験手数料は職種により異なりますので、確認してください。
〇合格発表は?
例年、上期は9月下旬に、下期は3月中旬に発表があります。
試験後、1か月ほどありますが、じっくり待ちましょう。
〇まとめ
本記事では技能検定について解説しました。
現場で働く方の技能の証明になることはもちろん、研究者・技術者等にとっても、その取得の過程で実験に必要なノウハウ等を取得できるため、有効な資格です。
私も技術者ですが、この資格の受験を通して得たノウハウは大いに役立っています。
ぜひチャレンジしてみてください。





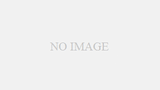

コメント